美しい日本語――
風景を宿すことばたち
日本語は美しい。
日々あたりまえのように使っていながら、ふとした一語に立ち止まり、その表現の豊かさや情緒にハッとさせられることがある。
言葉は、人々のものの見方や価値観をかたちにしたものだ。
単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、語彙や文法、音の響きの背後には、その言葉を話す人々の歴史や風土、価値観が折り重なっている。
異なる言語を学んでいると、それぞれの言葉が世界をどのように切り取り、どう描き出そうとしているのかが見えてくる。
同じ出来事でも、使う言語が変われば、焦点の当て方や込められたニュアンスは変わる。
その違いに、何度も驚かされてきた。
その中でも、日本語はひときわ繊細で、情景を呼び起こす力の強い言語だと感じる。
たった一語で季節の風景が広がったり、目に見えない心の揺らぎをすくい取ったりする言葉がいくつもある。
ほかの言語に訳そうとしても、どうしても取りこぼしてしまうような、精妙さと情緒を湛えた表現も少なくない。
日本語は、音と文字だけでできているのではない。
その背後には、この国の風景と、人々の心が宿っている。
ここでは、そうした「美しい日本語」を通して、言葉の奥にひろがる情景や感情の世界を紐解いていきたい。
蝉しぐれ(せみしぐれ)
真夏の昼下がり、森や公園に足を踏み入れると、あたり一面を埋め尽くすような蝉の声が降り注ぐ。
日本語では、この一帯を包み込むような蝉の鳴き声を「蝉時雨(せみしぐれ)」と呼ぶ。

「時雨」とは本来、晩秋から初冬にかけて降る細かな雨のことを指す言葉である。
その「時雨」を蝉の声に重ねることで、空から降るように響く鳴き声の密度や、あたりがふっとかき消されるような感覚を、ひとつの語に閉じ込めている。
蝉時雨は、単に「夏らしい音」というだけではない。
短い命の盛りに一斉に鳴き交わすその声は、生命の激しい躍動と、やがて訪れる静けさとを同時に意識させる。
力強く鳴り響くその響きの奥には、どこか儚さが滲んでいる。
逢魔が時(おうまがどき)
一日のうちで、もっとも不思議な時間帯がある。
夕暮れ時──あたりがほの暗くなり、昼と夜の境が曖昧になっていくそのひとときを、日本語では「逢魔が時(おうまがとき)」と呼ぶ。

光と闇が混ざり合う不思議な時間。まるで現実と非現実の狭間に立つような感覚に襲われることがある。
古い用例では「大禍時(おおまがとき)」と書かれ、「大きな禍(まが)の起こりがちな時刻」、すなわち不吉なことが起こりやすい夕方の薄暗い時間を指す語とされてきた。
のちに「禍(まが)」が「魔」と結びつけて解釈され、「大魔が時」や「逢魔が時」といった表記が生まれ、「魔に逢う時」という意味合いが強く意識されるようになった。
光と闇がまじり合い、見慣れたはずの風景が、ふいに別世界のように見えてくるその瞬間。人の心には、得体の知れないざわめきと、なぜか懐かしさにも似た感情が同時に浮かび上がる。
逢魔が時とは、現実と非現実、此岸と彼岸の狭間にある時間だ。
日本語は、そうした曖昧で不思議な感覚を、この一語でそっと言い表している。
木漏れ日(こもれび)
穏やかに晴れた日、木々のあいだから地面に落ちる、やわらかな光。
その情景を一語で言いあらわすのが、「木漏れ日(こもれび)」である。

私が日本語ということばそのものに強く惹かれたきっかけも、この「木漏れ日」という一語だった。
葉と葉のあいだから「こぼれ落ちる」光と、その場に満ちる暖かなぬくもりまでをも見事に一言で言い表してしまう。
その精妙さに、驚きとともに強い印象を受けたのを覚えている。
英語に置き換えようとすると、
“Sunlight filtering through the leaves of trees.”
といった説明的な言い方になり、情景は伝わっても、そこに漂うぬくもりや、情緒まで表現することが出来ない。
日本語の「木漏れ日」には、光そのものだけでなく、その場に流れる時間や空気のやわらかさまでを包み込むニュアンスが宿っている。
「木漏れ日(こもれび)」という言葉は、木々の葉の間からこぼれる日差し、そしてその暖かな雰囲気までも見事に一言で表す言葉である。
風景と感情がひとつになって立ち上がる──。
「木漏れ日」は、まさにそんな日本語ならではの美しさを体現したことばである。
夜の帳(よるのとばり)
「帳(とばり)」とは、本来、空間の仕切りや覆いとして使われる布を指す言葉である。
舞台の幕や、蚊帳、御簾(みす)などにも用いられ、「視界を遮るもの」「空間をやわらかく隔てるもの」としての役割を持っている。
日本語では、夜が静かに訪れることを「夜の帳が下りる」と表現する。
眩しい昼の景色の上にそっと布がかけられ、音や光がやわらかに吸い込まれていくような感覚。
“夜になる”という事実を、ただの時間の変化ではなく、心に染み入る情景として捉えているのが、この言い回しの美しさである。
夜が舞台の幕のように降りてきて、景色の輪郭を少しずつ曖昧にしていく。
光と音がゆっくりと引いていき、代わりに静けさが満ちてゆくその瞬間を、「夜の帳」というひと言が、静かにすくい上げている。

雪化粧(雪化粧)
「雪化粧(ゆきげしょう)」とは、山や木々、屋根などがうっすらと雪に覆われた様子を表す言葉である。
まるで白粉をはたいたように、柔らかな白が風景をそっと包み込み、冬の訪れを静かに告げる。
「雪が積もる」ではなく「雪化粧をする」と言うとき、日本語は自然をただの景色としてではなく、表情を持つひとつの存在として捉えている。
そこには、自然を敬い、その変化に美を見出すまなざしが伺える。
晩秋の彩りを終えた山が、ある朝ふと白くなっていたとき、人々は「山が雪化粧した」と言う。
そのひと言は、単に気象の変化を伝えるだけでなく、その風景に宿る静けさや厳かさ、季節の移ろいを喜ぶ気持ちまでも、やわらかく言いあてている。
雪が降るたびに、世界は違った表情を見せる。
「雪化粧」という言葉は、そんな儚くも気高い一瞬の美しさを、やさしく包み込んでくれる。

雪化粧を施した山々
もののあはれ
「もののあはれ」は、平安の物語や和歌に流れる、移ろうものごとにふと心を揺さぶられる感性を指す言葉である。
のちに江戸時代の国学者・本居宣長が『源氏物語』を読み解く中で、この感性を説明する鍵として語り広めたとされている。
それは、喜びや悲しみといったはっきりとした感情ではない。
季節の変わり目にふと覚えるさみしさや、何気ない風景に呼び起こされる記憶のような、言葉に出来ない曖昧な心の動きである。
人生も自然も常に変わり続けるという事実を見つめ、その無常の中ににじむ美しさや切なさを静かに受けとめようとする感性。
人の心は、本来、白か黒かでは語れない。
ひとつの出来事に喜びと切なさが同居し、すべての感情を言葉にできるわけでもない。
常に移ろい、変わってゆくものであるからこそ、その一瞬がいっそう尊く感じられるのだろう。
「もののあはれ」という言葉には、そうした日本人の感性が静かに息づいている。

日本語には、ひとつの響きのうちに景色や時間、人の心の揺らぎまでもが幾重にも折り重なっている。
他の言語ではいくつもの説明を重ねなければ届かない情景が、日本語では、たった一言で立ち上がることがある。
それは、単なる言葉のかたちの違いではなく、この世界をどう見つめ、どこに心を留めてきたのかという感性の違いなのだろう。
移ろいゆく自然や一瞬の心の揺れに耳を澄まし、それをことばに映そうとしてきた営みが、日本語という言語をかたちづくってきたのである。
日本語には日本語にしか描けない世界がある。
その豊かさに気づくことは、日本人の内に息づく美意識を、そっと呼び覚ましてくれる。
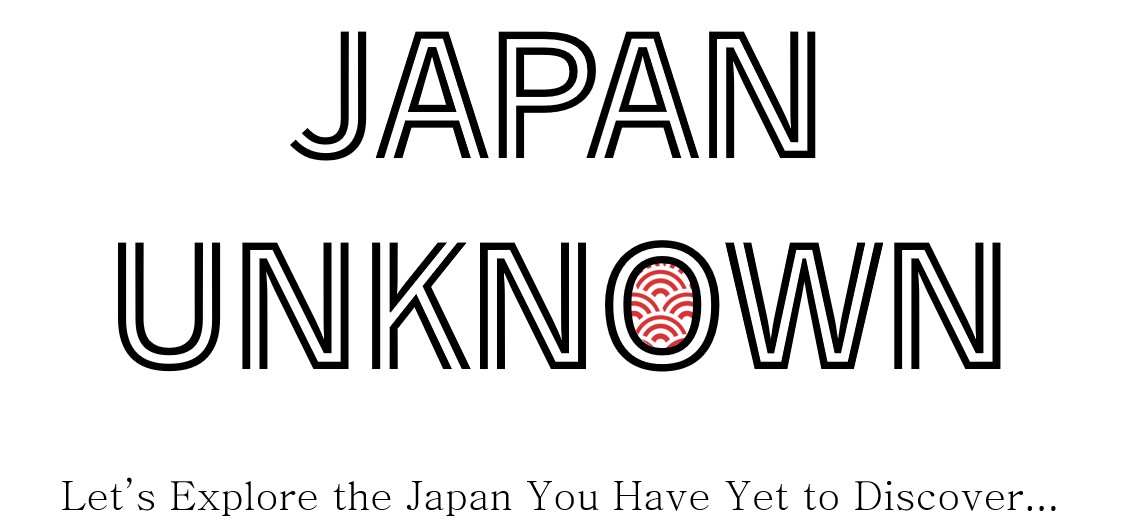
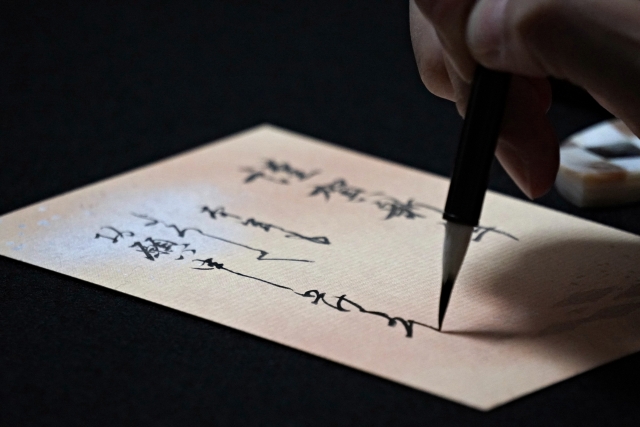



コメント