幸せを招く猫――招き猫に込められた日本人の心
静かに片手を上げてこちらを見つめる小さな猫。
日本の商店や家の玄関先など、さまざまな場所でその姿を見ることができる。
店先では客を招き、家では福を招く。
人々の暮らしの片隅に、当たり前のように存在しながら、どこか不思議な温かみと安心感を与えてくれる。
招き猫(まねきねこ)──それは福を呼ぶ猫として、日本の風景の中に自然に溶け込んできた存在である。
江戸の町で生まれた、福を呼ぶ伝説
招き猫の起源については、いくつかの伝承が語り継がれている。
中でもよく知られているのが、東京都世田谷区の曹洞宗寺院・豪徳寺(ごうとくじ)にまつわる話だ。
ある日、一人の武士が一匹の白猫に手招きされ、寺の境内へと足を踏み入れた。
すると直後に雷雨が来たため、武士は雨を避けることができたという。
後にこの武士は、彦根藩主・井伊家の人物 であったと伝えられている。
彼は豪徳寺を篤く支援し、猫は「福を招いた存在」 として崇められ、その姿を模した置物(=招き猫)が広まったとされる。
現在の豪徳寺には、奉納された白い招き猫がずらりと並び 、伝承が“縁起物”として生き続けていることを実感させる。

多くの招き猫が並ぶ豪徳寺
一方で、もう一つの招き猫の伝承が語られているのが、東京・浅草の今戸(いまど)地区である。
江戸時代末期の記録によれば、浅草花川戸に住む一人の老婆が、貧しさから愛猫を手放した夜、夢に猫が現れ、「自分の姿を人形にすれば福徳を授かる」と告げたという。
老婆は目覚めると、言われたとおりに猫の姿を模した人形を作り、今戸焼として焼き上げた。
やがてその人形は浅草神社(三社様)周辺で売られるようになり、たちまち評判を呼んだ。
その猫の特徴的な姿──ふっくらとした体、丸い顔、胸の「丸〆(まるしめ)」の印は、「今戸焼・丸〆猫」として知られるようになる。

どこかとぼけたような表情が魅力の丸〆猫
どの伝承が“本当のはじまり”かは定かではない。
けれど共通しているのは、招き猫が偶然の幸運や日々の願いを受け止める存在として、人々の暮らしの中に置かれてきたという点である。
手のしぐさに込められた意味
招き猫がそっと掲げる、その小さな前足。
一見、愛らしい仕草に見えるこの動作には、はっきりとした意味があるとされている。
右手を挙げた猫は金運や財を招くとされ、左手を挙げた猫は人や縁、すなわち客を招く。
商いの場では左手を、家庭では右手を選ぶことが多いというのも、暮らしの中で求める「福」のかたちが少しずつ違うからだ。
また、両手を高く挙げた猫もある。
両方の幸運を願う姿として受け取られることもあれば、「欲張りすぎてお手上げ」という、少し茶目っ気のある解釈が添えられることもある。
こうした多様なかたちの中に、願いの幅と、作り手の遊び心が同居している。

右手を挙げた猫は金運を、左手を挙げた猫は人や縁を招くとされている。
彩りに託される願い
招き猫と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、白い体に赤い耳、金の鈴、赤い首輪をつけた姿だろう。白は神聖さを、赤は魔除けを象徴するとされ、清らかさと守りの願いが重ねられてきた。
しかし近年では、その姿は一段と多彩になり、色ごとに、願いをより具体的に託す選択肢として定着しつつある。
白(開運招福)
最も基本とされる色で、招き猫の標準形として親しまれてきた。 「福を広く招く」という意味合いで、用途を選ばず置きやすいのが特徴だ。
迷ったときに白を選ぶ人が多いのは、その汎用性の高さによる。
黒(魔除け)
災厄や悪いものを遠ざける色として扱われることが多い。
店先では厄除け、家庭では防犯や安全祈願の意味で選ばれることがある。
「守り」を前面に出したいときの定番色である。
赤(無病息災)
赤は古くから病除けの色として扱われてきた。
また、神社の鳥居や祭礼の装束に見られるように、赤は穢れを遠ざける色としても用いられてきた。
そのため赤い招き猫は、金運や商売繁盛よりも「家族が病気をせず、日々を無事に過ごす」ことを願う場で選ばれることが多い色である。
金(金運)
金運・財運を直接的に示す色として、商いの場で好まれやすい。
華やかさがあり、目に入りやすい点も店頭向きと言えるだろう。
「成果」や「上向き」を願う場面で選ばれることが多い。
青(学業成就)
青い招き猫は、受験や資格試験、昇進試験など「結果がはっきり出る勝負事」に合わせて置かれることが多い。
勉強机や書斎、子どもの学習スペースなど、日々手を動かす場所に置かれ、努力を途切れさせないための目印になる。
ピンク(恋愛成就
ピンクの招き猫は、恋愛の縁や良縁を願う色として近年定着した。
出会い、交際、結婚といった節目に合わせて置かれやすく、贈り物として選ばれることも多い。
恋愛に限らず、人間関係を円滑にしたいという願いを重ねて置かれる場合もある。
緑(健康・家内安全)
緑は、家族の健康と家内安全を願う色として選ばれる。
金運のように目に見える成果を求める色ではなく、家族が大きく体調を崩さず、家の中が荒れず、日々が滞りなく回ることを願う。
派手な幸運ではなく、当たり前が続くこと──そのささやかな願いを託された色でもある。

それぞれの色に、それぞれの願いが重ねられている
こうした色彩の変化は、現代の多様な価値観と、時代の変化をそのまま映していると言えるだろう。
願いが一様でないからこそ、猫たちはさまざまな色を纏い、それぞれの願いを背負って並んでいる。
土地と素材がつくる招き猫
色が「願いの種類」を示すものだとすれば、産地や素材はその土地の「風土」を映す。
同じ招き猫でも、つやの強い磁器、素朴な土人形、木の質感を生かした彫り物では、置いたときの存在感が変わる。
そこには技術の違いだけでなく、その土地が育ててきた美意識 や、習慣がにじむ。
瀬戸(愛知県瀬戸市)──焼き物の町がつくる「つや」と実用
※愛知について読む:ものづくりの伝統と都市文化が息づく中部の中核
瀬戸は日本を代表する焼き物である「瀬戸焼」の産地として知られている。
瀬戸焼は、日用品から工芸まで作風や用途の幅が広く、釉薬を使った色味や質感のバリエーションも多い。
そうした土台の上で作られる瀬戸の招き猫は、つやのある白さや均整の取れた仕上がりが際立ち、店先でも目を引く。縁起物でありながら丈夫で、日常の中で扱いやすい点も、瀬戸焼の招き猫の特徴である。

艶が美しい瀬戸焼の招き猫
今戸(東京・浅草周辺)──下町の土人形が残す「素朴さ」
※東京について読む:伝統と最先端が交差する世界都市
今戸の招き猫は、磁器の清潔感というより、土そのものの素朴さが前に出る。
ふっくらとした造形や、少し力の抜けた表情は、整いすぎない親しみやすさとして受け入れられてきた。
浅草という土地柄もあって、今戸の招き猫は「高級工芸」より「生活の縁起物」として置かれる場面が多い。
手元に置いて願いを託すという親近感が、その佇まいにも表れている。

今戸神社の招き猫
九谷(石川県)──上絵の色彩がつくる招き猫
※石川について読む:加賀百万石の伝統が息づく、文化と美の継承地
九谷は日本を代表する色絵磁器である「九谷焼」の産地として知られている。
鮮やかな上絵付けを特徴とし、その華やかさは国内にとどまらず海外でも評価され、九谷焼は国際的にも人気を集めてきた。
その持ち味は招き猫にも生かされ、輪郭線と色彩の重なりによって、縁起物でありながらまるで芸術品のような豪華さが目を引く。
また九谷の招き猫は、明治期以降に輸出品としても人気を得たとされ、縁起物でありながら「見せる」ことを強く意識した方向へ洗練されていった。
土地が育てた上絵の技術が、そのまま招き猫の表情と贅沢さに反映されている。

九谷焼の招き猫 美しく豪華な色彩が特徴
※九谷焼については別記事で詳しく解説:美しい日本の伝統工芸品 – 九谷焼の魅力
こうして見ると、「招き猫」というひとつの名のもとに集う猫たちは、それぞれの土地の技と心、願いと美意識をまといながら、時代とともに姿を変え、多様な表情を見せている。
共通するのは、その小さな体の奥に、誰かの幸せをそっと願う気持ちが宿っているということだ。
幸せを招く猫
今も日本の各地で、職人たちはひとつひとつの招き猫を手作業で仕上げている。
ろくろを回し、土を捏ね、筆を走らせ、表情を整える。最後の仕上げに込められるのは、つくる人自身の「願い」でもある。
誰かのもとに届いたとき、その猫がそっと寄り添う存在であるように──そんな静かな祈りが、ひとつひとつの猫たちに込められている。
日常の片隅に飾られた小さな姿は、過ぎゆく時代の中でも変わらず、人が人を想うこころの証として、静かに息づいている。
そして今日もまた、どこかの棚の上で、小さな猫がそっと手を上げて、目には見えない誰かの幸せを、静かに招いているのだろう。
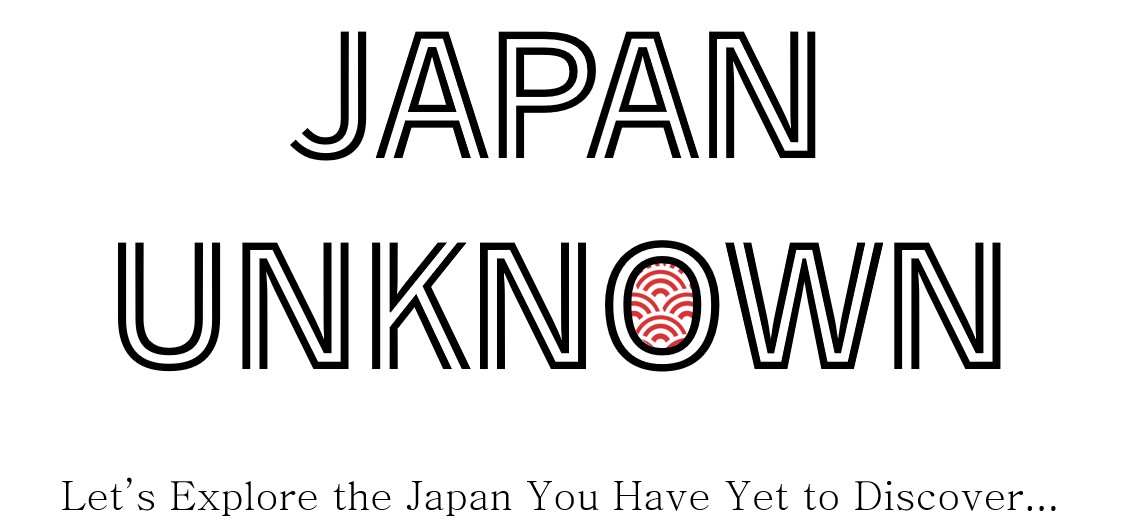




コメント