ふるさとの味探訪 ~岩手編~
本州北東部に広大な面積を誇る岩手県。
三陸の豊かな海、北上川流域の肥沃な大地、奥羽山脈に連なる山々――多彩な自然環境が織りなす恵みの中で、独自の食文化が育まれてきた。
長く厳しい冬を乗り越えるための保存食や、漁師や農家の知恵が生み出した郷土料理は、素朴でありながら滋味深い味わいを持つ。さらに、近年では個性豊かなご当地グルメや麺文化も全国的に注目を集めている。
今回は、そんな岩手県のふるさとの味を訪ねてみよう。
※岩手について読む:岩手県 | 美しい自然と伝統が紡ぐ日本の原風景
わんこそば(盛岡市、花巻市)

日本三大そばの一つにも数えられる「わんこそば」
岩手を代表する郷土料理といえば「わんこそば」。
小さなお椀に一口大のそばが次々に投げ込まれ、食べる者は途切れることなく受け続ける独特の形式が特徴だ。食べ終えたいときには椀に蓋をして合図を送る習わしがあり、これが終わりの区切りとなる。
※わんこそばについては別記事でも解説:日本人と蕎麦
もともとは客をもてなすために生まれた文化であり、その賑やかさや楽しさも味の一部。
長野県の戸隠そば、島根県の出雲そばと共に、日本三大そばの一つとされる。
盛岡冷麺(盛岡市)

盛岡冷麺はスイカや梨、リンゴなど季節の果物を添えるユニークなスタイルが特徴だ。
「盛岡冷麺」は、韓国冷麺をルーツに持ちながら独自の進化を遂げた一杯である。
冷麺は日本全国に存在するが、盛岡冷麺は特に強いコシをもつ小麦粉主体の弾力がある麺、牛骨を煮出した澄んだスープが特徴。またキムチやチャーシュー、ゆで卵といった定番の具材に加えて、りんごや梨、スイカなどの果物を添えるのもとてもユニークな特色だ。
果物の甘みと酸味がスープの辛味を引き立て、独特の爽快感を生み出す。
焼肉店の締め料理として広まり、いまでは一年を通じて市民に親しまれる、盛岡を代表する味覚となっている。
じゃじゃ麺(盛岡市)

わんこそば、盛岡冷麺と合わせて「盛岡三大麺」と言われる「じゃじゃ麺」
わんこそば、盛岡冷麺と合わせて「盛岡三大麺」と言われるのが、「じゃじゃ麺」だ。
中国の炸醤麺をルーツに持ち、戦後に盛岡へ移り住んだ料理人が広めたのが始まりとされ、市内各地の食堂や専門店に定着していった。
太めの平打ち麺に、肉味噌とキュウリ、ネギをのせ、よく混ぜて食べる。
食べ終えた後は、皿に残った肉みそに卵とスープを加えて作る「チータンタン」というスープを楽しむのが定番である。
素朴ながらも自由に味を調えられる楽しさがあり、にんにくや酢、ラー油などを加えて好みの味に仕上げることができる。
こうした食べ方の幅広さが魅力となり、盛岡の食文化を語る上で欠かせない存在となっている。
前沢牛(奥州市)

日本を代表するブランド和牛「前沢牛」
岩手県南部、奥州市前沢地域で育てられるブランド和牛「前沢牛」。
きめ細やかな霜降りは芸術品のように美しく、一口ふくめば脂が体温でとろけ、濃厚な旨みが広がる。
その肉質は全国の品評会でも高く評価され、名実ともに日本を代表する和牛の一つとして知られている。
地元ではステーキやすき焼き、しゃぶしゃぶ、焼肉など多彩な料理で味わわれ、その旨みの濃さと脂の甘さは格別。
贈答用としても人気があり、岩手を代表する高級食材となっている。
丹精込めて育て上げられた一頭一頭が、豊かな自然と生産者の情熱を映し出す、岩手が誇る極上の味覚である。
ひっつみ(県内各地)

岩手の農村に古くから伝わる家庭料理「ひっつみ」
岩手の農村に古くから伝わる家庭料理「ひっつみ」。
小麦粉の生地を手でちぎって鍋に落とし、鶏肉や野菜と一緒に煮込む素朴な汁物である。
名前の由来は「生地を手でひっつまんで入れる」ことから。
モチモチとした食感と、具材のうまみを吸った優しい味わいが特徴で、寒い冬に体を温めてくれる。
決して派手さはないが、家庭の温もりを感じさせる、まさにふるさとの味である。
北上コロッケ(北上市)
岩手県南西部に位置し、東北有数の工業都市である北上市は、里芋の生産地としても知られている。
この地域の特産である二子里芋は、粘りが強く煮崩れしにくいのが特徴で、地元の誇りとして古くから親しまれてきた。
その魅力を生かして誕生したのが「北上コロッケ」である。
ホクホクとした里芋のやさしい甘みに、北上牛や西和賀産ほうれん草など周辺地域の食材を合わせ、外はサクッと香ばしく、中はとろりと滑らかな食感を実現した。

北上コロッケは、粘りが強く煮崩れしにくい「二子里いも」から作られる
まちおこしの一環として生まれたご当地グルメだが、今では市内の飲食店や家庭でも広く愛され、北上の新しい名物として定着している。
まめぶ(久慈市山形町)

岩手県北部、久慈市山形町に伝わる郷土料理「まめぶ」
岩手県北部、久慈市山形町に伝わる郷土料理「まめぶ」は、素朴ながらも滋味あふれる伝統食だ。
小麦粉の生地でクルミと黒砂糖を包み、野菜や豆腐と一緒に醤油味の汁で煮込む。甘じょっぱい独特の味わいは、寒さ厳しい土地で培われた知恵と工夫を映し出すもの。
かつては祝い事やハレの日に欠かせない一品で、家族の団らんを象徴する料理でもあった。
2013年に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「あまちゃん」に登場したことで全国的に知られるようになり、岩手の食文化を象徴する一椀として注目を集めている。
もち料理(岩手県全域)

もち御膳
岩手県は、全国でも有数の「もち食文化」が根付く地域である。
農村部を中心に、正月や冠婚葬祭など人生の節目ごとに餅がつきものであり、その伝統は数百年にわたって受け継がれていると言われる。
多彩な餅の種類や食べ方が存在し、単なる正月食ではなく、日常と儀礼の両面で餅が深く根づいているのが特徴だ。
特に顕著なのが「もち本膳」のしきたりだ。
冠婚葬祭など改まった席で供されるもち本膳は、なます(大根おろし)を口にしてから、あんこ餅→料理もち→雑煮と順にいただき、最後にたくあんで器を拭って終えるという決まりごとがある。
こうした一連の作法は、単なる食事を越えた儀礼であり、地域ごとの細かいルールや作法が今も伝承されている。

岩手の食文化は、厳しい自然と豊かな風土、そして人々の知恵と工夫が織りなしてきたものである。
豪快で賑やかなものから、素朴で温もりのある家庭料理まで、その幅広さは実に多彩だ。
食を通じて土地の歴史や暮らしぶりが見えてくるのも、岩手ならではの魅力といえるだろう。
ふるさとの味探訪シリーズ
・北海道編 : ふるさとの味探訪 ~北海道編~
・青森編 : ふるさとの味探訪 ~青森編~
・秋田編 : ふるさとの味探訪 ~秋田編~
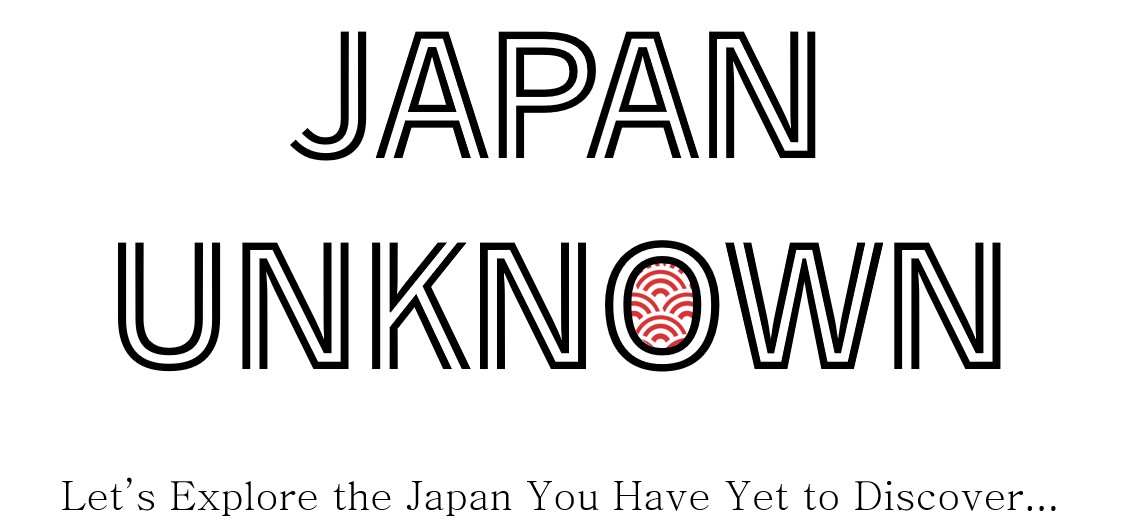




コメント